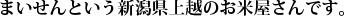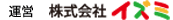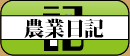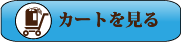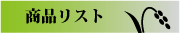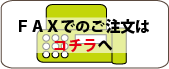- HOME
- 米選のススメ
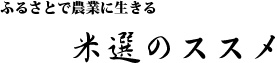
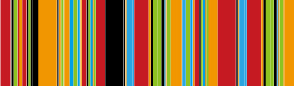
-

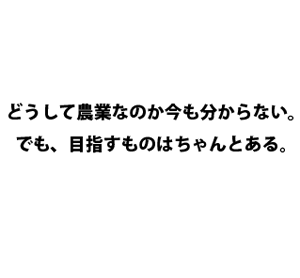 2010年2月28日 新潟日報 「新潟エンブレム」
2010年2月28日 新潟日報 「新潟エンブレム」「稲刈りって、1年に1回しかないんです。この日のために農家の365日がある。見渡す限り金色で、風がさ〜っと渡って。感無量でした。最初の年は泣きそうになった」。この瞬間が農業の面白さだと言う。農家になるつもりは全くなかった。どうしてこの仕事を選んだのか、今考えてみても分からない。
大学4年の夏。教員採用試験の会場へ向かう電車の中で、楡井さんは今から受ける試験に集中していた。ところが電車を降りた瞬間、「あれ?これは違う」と思った。そのまま家に電話をかけ、家で働かせてほしいと頼む。誰にとっても、思いがけないことだった。 「ず〜っと頭の中にあったのは、おやじに抱かれている僕の写真。2歳の頃だと思うんですけど、父の後ろにはトラクターがあって、かっこいいんです」楡井農場は両親と楡井さん本人、伯父2人とスタッフ2人の7人で働き、農地は33ヘクタール。上越市では大規模な方に入る。両親は「世間知らずを家に入れるわけにはいかない」と、息子を知人の会社に勤めさせた。「やめるなら今のうち」という、猶予でもあった。 勤めた2年は、決意がゆるがなかったというより「考える時間がなかった」と言う。新卒の青年に、新規立ち上げの事業が任された。「従業員募集、面接、支払いまでやりました。家に帰れない日もあって、目の前の課題をクリアすることだけで毎日精いっぱい」という楡井さん。おかげで真夜中だろうがやらなくてはならないことはやる癖がついた。「農業の楽しいところしか見えていないと親に言われたその通り。仕事ってこういうものなんだって勉強させてもらいました」
楡井さんが、父の知人の会社で勤めたように、楡井農場もまた、知人の息子を受け入れている。父の世代の就農者で作った「いぶきの会」は、今はこの世代がその中心となった。「おやじのころは柿崎の農家だけだったんだけど、今は人数が減ってエリアが広がった。どこの集落だろうが、年齢も関係なく、農業をやっているって、それだけでつながっていられる」と言う。顔の見えるたちと助け合ってゆく日常。楡井さんはその中で育ち、これからも生きていく。今、農業をめぐる環境は、めまぐるしく変化している。昨年はインターネットによる委託販売を始めた。日々の段取りや販売会社との折衝に追われる中で、戸惑いもある。「本当は、手渡しできる人に食べてもらいたい」それが当面の目標になった。食べる人にはどんな場所で、どうやって作っているのかを知ってほしい、自分は誰が食べているのか分かって作りたい。自分をはぐくんでくれる地域の力も地域の力もおすそ分けしたい。そのためにどのようにすれば良いのか、まだよく分からない。
「食うときにね、ご飯とおかずを食べるじゃないですか。その時に田んぼのことを思い浮かべると、頭の中におかずが1個。ちょっと幸せでしょ?」と言って笑った。楡井聡・にれいさとし●1981年生まれ。水戸市の大学を卒業後、上越市内で会社員。現在は上越市柿崎区で、稲作のほか白菜、春菊を栽培する専業農家を営む。
「心のなかのふるさとのカタチ 新潟エンブレム」 2010年2月28日 新潟日報記事内より転載